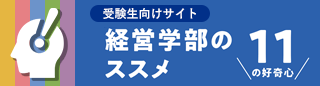- ホーム
- 学部・大学院
- 法学部|教員紹介|法学部専任教員
- 教員紹介詳細
教員紹介詳細
| 教員氏名 | 阿部 徳幸(アベ ノリユキ) |
| 職名 | 教授 |
| 最終学歴・学位 | 日本大学法学部卒 法学士 税理士 |
| 専門分野 | 税法 |
| 学協会活動 | 日本租税理論学会常任理事 宗教法学会理事 韓国租税研究フォーラム会員 |
| 【主な著書・論文等】 |
|---|
|
(論文) 1.「消費税の再検討」(単著 2023年 『日本法学88巻4号』) 2.「韓国における納税者権利保護の動向」(単著 2020年『租税上の先端課題への挑戦』) 3.「大韓民国国税基本法第7章の2納税者の権利の概要」(単著 2015年 『日本法学80巻4号』) 4.「改正された税務調査手続と宗教法人」(単著 2014年 『宗教法学会誌宗教法第33号』) 5.「韓国国税庁『Greenbook2013』にみる税務調査手続の概要」(単著 2014年 『『関東学院法学第23巻第3号』) (著書) 1.『税法がわかる30話(第2版)』(単著 2022年 中央経済社) 2.『税金のすべてがわかる現代税法入門塾 第12版』(共著 2024年 清文社) 3.『税理士・弁護士が知っておきたい滞納処分の基本と対策』(編著 2018年 中央経済社) ◆◆◆◆◆ その他 研究内容・学生へのメッセージ ◆◆◆◆◆ 【問題関心】 税理士として、税務行政の現場にいると「国民・納税者」には、税における「義務」ばかりが強調されているようにしか思えない。わが国は民主主義国家であり、憲法は国民主権をいう。だとすれば「国民・納税者」は、税においての客体にとどまらず、権利者であり同時に主体者でなければならない。諸外国を見渡すと、このことを意識してか、競い合うように納税者権利保護法(権利憲章)を制定している。しかし、我が国においてはいまだその兆しすら見られない。いずれの国においても財政危機がいわれて久しい今日、この危機を乗り越えるためには国民・納税者と国家が手を取り合って対処する必要があるはずである。税法とは果たして国民・納税者の義務のみを定めたものなのか、はたまた義務と同時に税法上の権利までをも規定したものなのであろうか。さらにはわが国唯一の「税務に関する専門家」である税理士に求められる本来の役割、使命とはどいうあるべきなのであろうか、このような問題点に関心を寄せています。 【現在の研究テーマ】 ①税務行政手続のあり方・納税者権利憲章の研究:近年OECD加盟国では租税負担率の上昇に伴い、財政運営における納税者の権利保護が重要な課題となっている。その対策として欧米各国では、納税者権利保護法(権利憲章)が制定されている。しかし、日本ではまだ法整備がなされていない。そして現状の行政優位体制のままでは法制定は未だ遠い。そこで諸外国における納税者保護法(権利憲章)の研究を行い、これを基礎にわが国における法制定の必要性を見いだしたい。そのうえで、わが国における納税者保護法(権利憲章)の具体的あり方をも研究する。 ②税制調査会「答申」の分析と提言 税制調査会の公表する「答申」は、毎年の税制改正に多大な影響を与える。この「答申」を分析するとともに、あるべき税制を人権論の視点から研究する。 ③税理士制度の研究 申告納税制度を支える税理士制度のあり方について研究する。 ④宗教法人法制と税制のあり方 宗教法人は、宗教的事項と世俗的事項を扱う。いわば「聖」と「俗」の両面を扱う法人である。この「聖」の部分、すなわち宗教活動に課税という形の公権力の行使は、憲法の保障する信教の自由に抵触することとなる。この「聖」と「俗」の接点上の課題を取り上げ、研究する。 【学生へのメッセージ】 学生諸君にとって「税」の問題は非常に身近な問題のはずです。しかし、同時に非常に遠い存在だと思ってしまうのも実情です。こんな性格を持ち合わせた「税」について皆さんと考えてみたいと思います。そのためには、みなさんに「わかった」と思っていただけるような授業でなければなりません。「わかった」と思えるようになれば授業も楽しくなるはずです。具体的には今日の授業の内容が、現実の税務行政の現場ではどのようになっているのかということも紹介しつつ授業を進めていきます。さらには「明るく、楽しく、元気よく」を目標に、みなさんと税法を学んでいきたいとも思います。そのため授業中のスマホいじりは厳禁とします。一生懸命勉強しようとしている他の方に失礼です。 |