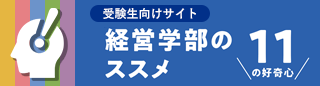- ホーム
- 学部・大学院
- 法学部|教員紹介|法学部専任教員
- 教員紹介詳細
教員紹介詳細
| 教員氏名 | 佐竹 壮一郎(サタケ ソウイチロウ) |
| 職名 | 講師 |
| 最終学歴・学位 | 同志社大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程後期課程修了・博士(政治学) |
| 専門分野 | 現代ヨーロッパ政治 |
| 学協会活動 | 日本EU学会、日本国際政治学会、日本政治学会、グローバル・ガバナンス学会(理事) |
| 【主な著書・論文等】 |
|---|
|
業績は以下のリサーチマップをご確認ください。 https://researchmap.jp/ssatake ◆◆◆◆◆ その他 研究内容・学生へのメッセージ ◆◆◆◆◆ 【問題関心】 私の専門分野は現代ヨーロッパ政治、特にEUの動向に関心をもっています。現在27か国からなるEUはしばしば国家でも国際機関でもない「独特な」政体と評されてきました。私の問題関心は、こうしたモヤモヤした存在であるEUにおける変化と現状維持の政治力学を捉えることにあります。 【現在の研究テーマ】 上記力学を捉えるため、現在の研究テーマとして、EUにおける民主主義の赤字と権威主義化の相互的影響の解明を掲げています。 近年、世界各地で権威主義化や「民主主義の後退」が主要な論点となっています。しかしながら、権威主義体制の戦略性の高さが明らかにされる一方、民主主義体制の動向はその課題も含め十分に解明されていません。その最たる例としてEUが挙げられます。 EUは民主主義に基づく国際的な政治体制を自負しています。にもかかわらず、EU市民権が誕生したマーストリヒト条約の調印(1991)以降、EUは市民による民主的統御が行き届かない「民主主義の赤字」状態に陥っていると指摘されてきました。また、域内における世論の分極化や権威主義化が21世紀に入り確認されています。これまでの研究において両者は別個の課題として認識されていましたが、EUの現在を捉えるにはどちらか一方に着目するだけでは十分とはいえません。EUはどのように民意のくみ取り方を更新しているのでしょうか。また、域内における分極化や権威主義化にEUはいかに対応しているのでしょうか。こうした問いに回答するために、欧州市民発議や様々なオンラインプラットフォームの形成過程に焦点を当てて分析を進めています。 本研究を通じて、「権威主義対民主主義」論の死角がより具体化され、また統合を進める民主主義体制の構築・維持・変容のメカニズムに関する新たな知見がもたらされます。さらに、民主主義と権威主義の相互的な影響や共通性をめぐる研究は今後さらなる発展が望まれている分野です。こうした研究動向の中で、本研究は「独特」と評されるEUを比較可能な参照軸として再提示する役割を果たし、地域統合研究の進展や国際秩序に着目する研究への波及効果も期待できます。 【学生へのメッセージ】 私が1人の研究者、そして社会人として意識していることは次の3つです。第1に、「普通」間のズレにおける対話です。家族における「普通」、学校における「普通」、日本における「普通」、世界における「普通」は必ずしも一致しているわけではありません。この「普通」間のズレを本格的に学ぶ場が大学だと私は考えています。つまり、大学は自分自身が案外中立ではないだけでなく、誰もが偏っていることを理解する場なのです。この作業は心地の良いものではなく、むしろイライラ・モヤモヤするものです。それでも、生の感情をそのままぶつけ合うことが「普通」と化した今だからこそ、互いに対する尊重に基づき、丁寧に、本音で議論する経験を大学で積むことが必要だと信じています。 第2に、習慣としての仕事です。よく「好きなことが仕事で良いね」と言われます。ただ、私はアニメは好きだといえる一方、大学教員の仕事を好きだと思ったことはないです。それでも、研究や授業について考えることは習慣化しています。つまり、私にとって仕事は歯磨きに近いです。歯磨きに好き嫌いという感情をもったことはないですが、しないと非常に気持ち悪いです。「好きなことを見つけなきゃ」と焦る気持ちは分かります。ひとまず、小さな習慣から始めてみてください。そのうち「好きなことがあって良いね」と言われるようになると思います。 最後に、失敗からの成長です。18歳の私は第3志望の大学にさえ行けず、当時は「人生終わった」と思っていました。ところが、今の私からするとそれは数ある失敗の1つにすぎません。むしろ、第4志望の大学を起点とした素敵な出会いの数々がなれけば、私は大学教員になっていなかったと思います。そろそろ「余裕ある大人」になっている予定だったのですが、学会でも、何気ない雑談でも失敗して、度々「1人反省会」を開催しています。それでも、研究者としても人間としてもまだまだ成長できると前向きに捉えています。大学には、失敗しても挑戦し続けるあなたを応援する人であふれています。一緒にたくさん失敗していきましょう。 |