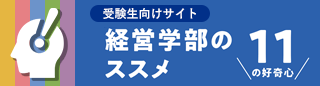教員紹介詳細
| 教員氏名 | 藤野 裕(フジノ ユタカ) |
| 職名 | 准教授 |
| 最終学歴・学位 | 立教大学大学院経済学研究科博士課程後期課程単位取得後退学 |
| 専門分野 | 会計学 |
| 学協会活動 | 日本会計研究学会、会計理論学会 |
| 【主な著書・論文等】 |
|---|
|
〔論文〕
(単著)「ケインズの使用費用概念―経済学と会計学の接点―」2007年、立教経済学研究第60巻第3号 (単著)「裁量的会計発生高推定モデルの現状と新たな課題―モデルが仮定する条件の現実妥当性について―」2009年、立教経済学研究第62巻第3号 (単著)「会計学における不確実性の役割」2014年、四日市大学論集第27巻第1号 (単著)「マイナス金利に影響を受ける会計上の問題について」2018年、明海大学経済学論集第30巻・第2号 (単著)「会計数値の比較可能性に関する一考察」2020年、富山短期大学紀要第56巻 〔著書〕 (共著)『経済学における数量分析―利用と限界を考える―』2008年、産業統計研究社 (共著)『経済系のための情報活用1 Office 2019 対応 統計データで学ぶ情報リテラシー』2019年、実教出版株式会社 (共著)『経済系のための情報活用2 Office 2019 対応 統計データの分析』2020年、実教出版株式会社 ◆◆◆◆◆ その他 研究内容・学生へのメッセージ ◆◆◆◆◆ 【問題関心】 経済学と会計学の接点について関心を持っている。両者は異なる学問分野だが、企業の意思決定、財務報告、政策分析などにおいて密接に関連している。 たとえば、経済学と会計学は、企業の意思決定における会計情報の役割に関する研究で交差する。企業が会計情報をどのように活用して、生産や価格設定、投資判断などの意思決定を行うのかについて考察を行うことで、会計情報が企業の株主価値や企業の市場競争力に与える影響を研究している。 また、企業の価値評価(企業価値や株式価値)に対して会計上の指標(例えば、利益や純資産など)がどのように影響を与えるか、またその影響を経済学的に分析することにも関心がある。 さらに、非財務情報(例えば、ESG:環境・社会・ガバナンス)が企業の価値に与える影響について、経済学と会計学を融合させて、これらの非財務情報がどのように経済的意思決定に影響を与えるか、またその測定方法について研究している。 【現在の研究テーマ】 会計学の本質についてプラトンの「イデア論」とウィトゲンシュタインの「家族的類似」の観点から哲学的な考察を行っている。 プラトンのイデア論に基づけば、理想的な会計情報(完全に透明で、正確な情報を提供する財務報告)という「イデア」が存在する。しかし、プラトンのイデア論では、私たちが感覚的に知覚するものはすべて「影に過ぎない」とされ、真の実在はイデアの世界にあるとされる。会計学における報告書やデータも同様に、企業の実際の「姿」を完全に捉えたものではなく、あくまでその「影」であるという考え方をすることで、企業の財務諸表や会計情報は、あくまで企業の「現実」の一部に過ぎず、完全に実態を反映したものではないという点で、プラトンのイデア論との類似性を見出すことができる。また、プラトンの哲学には、倫理的な理想が強調されており、真理や正義は感覚的な世界を超越するものであり、理性によってのみ理解される。会計学でも、倫理的な観点から、企業の透明性や公正な財務報告が重要視され、これは実際の会計報告における目指すべき「イデア」として考えることができる。そのため、企業が倫理的に正しい情報を提供することが求められるという点においてプラトンの思想と一致する。さらに、プラトンのイデア論に照らし合わせると、時代の変化に応じて新しい規則やガイドラインが作られるといった会計基準の進化は、現実世界におけるイデアの「変容」とみなすこともでき、現実の会計基準は、完璧な「会計イデア」を追求する過程であると捉えることもできる。 一方、ウィトゲンシュタインの家族的類似の概念は、ある物事が他の物事と似ている場合、それらの類似点がひとつの本質的な特徴に基づくのではなく、複数の部分的な類似性に基づいているというものである。会計学においても、財務報告や会計基準には、明確に定義された「共通の特徴」が一義的に存在するわけではなく、異なる企業や業界が、それぞれの状況に応じた会計処理を行いながらも、共通の目的—すなわち、経済的な意思決定をサポートすること—を持っている。例えば、企業ごとに異なる業種や規模に応じて異なる会計方法が用いられることがある一方で、全ての会計実務には「透明性」「正確性」「公正性」といった類似点が存在する。これが「家族的類似」の考え方に似ていると考えている。ウィトゲンシュタインは、概念や言葉が厳密に定義できるわけではないことを示し、代わりに「家族的類似」を用いることで、概念の多様性を説明した。会計学においても、「会計」とは何かという定義には厳密な境界が存在するわけではない。例えば、財務会計、管理会計、税務会計、社会的会計など、それぞれの会計分野が持つ特徴や目的は異なるが、それらはすべて「会計」という大きな枠組みの中で、何らかの「類似点」を共有している。会計学における「家族的類似」とは、会計の異なる領域や実務が、明確な定義で一貫性を持つのではなく、相互に重なり合う部分があり、実務や目的が異なる中でも共通の「目的」や「価値」を追求しているという点で考えることができる。さらに、ウィトゲンシュタインは、概念が時とともに変化し、異なる状況や文脈によって意味が変わることを指摘した。会計学においても、会計基準や会計実務は経済環境や技術の進展に応じて進化し続けており、デジタル化やAI技術の進展により、従来の会計実務や基準が変化している現代においても、「会計」という概念は依然として重要ではあるが、その具体的な内容や方法は常に進化している。この進化する「会計」の概念も、家族的類似のように、一貫した定義があるわけではなく、多様な側面が相互に関連しているという点で捉えることができる。ウィトゲンシュタインの家族的類似の考え方は、会計実務がその多様性を受け入れつつ、共通の目的に向かって進化する過程とも関連している。財務報告の形式や内容は、多くの異なる要因(法規制、企業文化、業界慣行、国際基準など)によって影響されるため、単一の定義や形態で捉えることはできないが、すべての会計報告には、「透明性」「一貫性」「信頼性」といった共通する価値がある点で、家族的類似の観点から理解することが可能ではないかと考えている。 【学生へのメッセージ】 大学生活の中で、自分がどこにいるのか、何をしたいのかがはっきりしないこともあります。しかし、その時期に焦る必要はありません。今の自分を無理に変えようとするのではなく、少しずつでも自分が興味を持っていることや、やりたいことを見つけていけばいいのです。後になって振り返ると、何気ない日々が大切な経験だったと気づくことがよくあります。今は「特に何もしていない」と思えるかもしれませんが、その中で培った人間関係や学んだことが、後々役立つ場面が必ずあります。今やっていることが、未来のあなたにどう影響を与えるかは、時間が経ってから分かるものです。焦らずに、自分を大切にすることが、最終的には成長につながります。 大学生活は、学問だけでなく、たくさんの経験をする大切な時期です。勉強以外にも、サークル活動、アルバイト、旅行、友人との交流など、様々なことに挑戦できる機会があります。思い切りいろいろなことにチャレンジしてみてください。どんな結果であれ、学びや気づきは必ずあります。重要なのは「何を達成したか」ではなく、「その過程でどれだけ成長したか」です。成功や成果ばかりに目を向けるのではなく、プロセスや自分自身の成長を大切にしてください。 |