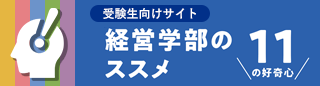学生による模擬裁判員裁判を7月16日と23日、本キャンパスの法廷教室で実施しました。これは法学部の平山真理教授が担当する「専門特講Ⅰ(刑事模擬裁判)」前期授業のまとめとして行われたものです。
学生らは2班に分かれ、それぞれ事案の作成や証拠の設定、証人尋問の内容などを準備してきました。各グループが1日ずつ実演し、経験豊富な弁護士の方々に総評をいただきました。
7月16日 強盗致傷被告事件についての模擬裁判員裁判
「被告人の女子大学生は、失恋のショックからホストクラブ等で散財し、多額の借金を負う。仕返しも兼ねて元恋人Aの家に侵入し、窃盗を続けるが事件当日Aに発覚。包丁で刺して逃走した」という設定です。被害者や被告人の父親などが証人として出廷しました。
閉廷後は、臨床心理士や公認心理師の資格も持つ安西敦弁護士(京都弁護士会)から「事実と意見を分けて、証人尋問や弁論を準備する」「主尋問・反対尋問、それぞれの効果的な手法」などを実践頂き、学生らはプロの手腕に感嘆しながら、多くを学びました。
7月23日 殺人未遂被告事件についての模擬裁判員裁判
「就活に苦しむ28歳の被告人が、ラーメン屋の店主と口論になり、包丁で刺して逃走した」という設定です。被告人は店主に対し大声で威嚇していましたが、当時の記憶が全くないと供述し、刑事責任無能力で無罪を主張しているという難しい事件でした。被害者や目撃者、また鑑定医等が証言をしました。
閉廷後は、70件以上の裁判員裁判の弁護を担当してきた村木一郎弁護士(埼玉弁護士会)に「同じ罪名の事件でも様々な要素が量刑に影響してくる」など具体的に解説して頂きました。
いずれの回も、傍聴していただいた方々の投票をもとに判決を決定しました。その結果16日は求刑8年に対し懲役6年、23日は求刑9年に対し懲役8年が言い渡されました。
平山真理教授コメント
学生らは事案の設定や証拠の整理などについても、自分たちで考えながら準備をしてきました。大半のメンバーは裁判傍聴の経験もなく、入学したばかりの1年生も多かったので、当初はみんな戸惑いながら準備していました。それでも準備が進むにつれて弁護人や検察官、裁判員といった各役が刑事裁判においてどのような役割を果たすのか、主体的に考えられるようになったと思います。今回は刑事弁護のエキスパートである先生方からも貴重なお話しをいただくことができました。学生も積極的に手を挙げ、様々な質問をしていたことが印象的でした。ご協力いただいた安西弁護士、村木弁護士にあらためて心から感謝申し上げます。

【16日】被告人(中央)に質問する弁護人(左)

【16日】熱の入ったコメントを学生に送る安西弁護士

【23日】会場となった法廷教室

【23日】裁判官および裁判員席の学生

【23日】学生の質問に答える村木弁護士